【MONOist掲載!ものづくり太郎のPLM講座第四弾!】金型の製作性2倍の爆上げを支えるPLM

MONOist連載!四弾目は、日本が得意とする『金型』に焦点を当てます!「すり合わせ」や「現場力」が強いとされる日本の製造業だが設計と製造、調達などが分断されており、人手による多大なすり合わせ作業が発生している。本日は、日本のお家芸とも言われた金型のPLM運用について取り上げたい。第4回は、金型製作におけるPLM活用の価値について紹介する。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー記事ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■量産を安価で効率的に実現する金型 筆者は商品認証企業を退職した後に、金型部品やFA部品を手掛ける専門商社であるミスミに入社することになるが、ミスミでの最初の業務は金型部品の営業に従事していた。ミスミが発刊している青色のプレス金型の本を持ち愛知~関西のお客様に対して奔走したのが、今では懐かしい。 当該記事を読む担当者は、おそらく製造業従事者であり、今から金型の説明をするまでは無いと思うが、念のため金型とは?から触れさせていただきたい。 金型は国力を表すと言われている工業品である。文字通り金属で構成された型を使い、精度を転写し様々な製品を生み出していく。金型の精度>製品になるので、金型の品質が製品の品質を決める。今使っているノートPCの筐体、キーボード、コネクタ類等、多くの製品が金型から生み出されており、金型を見れば工業レベルが分かると言われるわけである。射出成形、プレス、ダイキャストと様々な金型の種類があるが、本日はプレス金型を取り上げる。プレス金型は、金属製の金型をプレス機に搭載し、上型と下型の間に鋼板(ブランク)を通し、数十トン~数千トンに上る大きな力で上型を下型に押さえつけることで、間にある鋼板の形を変化させる塑性(そせい)加工である。単にプレス加工と言っても鋼板を切断、曲げ、絞る等の加工が可能であり、例えば自動車の筐体の多くの部品がプレス加工によって生み出されている。自動車の形はそれぞれ違うが、金型によってさまざまな形に成形する。プレス加工のロール材と製品の例 出所:協和工業のWebサイト https://kyowaindustry.co.jp/■金型の構成プレス金型は多くのプレートから構成される。トップホルダープレート、スペーサープレート、バッキングプレート、パンチプレート、外形ダイプレート等を重ね合わせていく。それぞれ金属で構成されているため、工作機械によって切削の精度を出しながら1個の金型を構成していく。もちろん、それぞれのプレートの精度が担保できなければ、最終的な金型の精度が出ないため、精度のすり合わせは非常に重要になってくる。プレートの精度だけではなく、プレートを重ね合わせるためのノックピンを押し込む穴精度や、ガイドポストやパンチやダイなどの部品を組み込むためのはめ合い精度等も鑑みながら構成していく必要がある。金型の製造は切削するのみだけではなく、切削するまでに様々な工程を経る。イメージを捉えてもらうため、自動車部品を例にとって説明を行う。自動車OEMや自動車のTier1は、多くの金型メーカーと取引があるが、年々部品の要求が高度化しており、部品毎に依頼する先はほぼ決まっている。依頼を受ける金型メーカーも仕事を受けながら、該当部品のノウハウを蓄積していく。依頼元はCADデザインを基に、金型メーカーとすり合わせを行い、部品形状を決めていく。金型メーカーもしくは、金型と、部品の製造までも行うメーカーはDR(デザインレビュー)の後に出図された図面を基に、金型部品の製造と、金型の構成部品の手配を進める。■金型PLMに関連する最近の自動車部品のトレンド金型のPLMの運用の話をする前に、自動車の構成部品のトレンドについても要点を紹介しておく。自動車部品のトレンドの概略が分かると、PLM運用のメリットも理解しやすくなるだろう。 最近の自動車は、一層の軽量化が求められており、プレスを行う鋼板も変化している。従来の単なる鋼板から、最近は高張力(引っ張り強度が高い)化し、薄くすることで軽量化できる鋼板に移ってきている。ハイテン材(高張力鋼板)といわれているものだ。 トヨタ自動車の第4世代以降のプリウスを構成する鋼板は、実に50%以上がハイテン材を採用している。さらに第5世代プリウスでは30%は超ハイテン材(引っ張り強度980MPa以上の鋼板)が採用されたといわれている。超ハイテン材は文字通り、ハイテン材からさらに高張力化され、軽量化を可能としたものだ。このようなハイテン材、超ハイテン材は、自動車の高性能化を支える重要な素材だが、高張力であるため、加工が難しくなる。超ハイテン材ともなると、引っ張り強度が強く形状をプレス加工することも容易ではない。スプリングバック現象(プレス成形した後に、鋼板が元の形に戻るように変化する)など加工後の形状も考慮に入れながら、プレスする金型の順番や形状を構成していかなければならない。 ハイテン材を加工する金型には、高剛性が求められるため金型の板厚を厚くしたり、一部の材料ではSKD材(ダイス鋼)ではなくハイス材や超硬材を活用したりしなければならない。つまり、加工コストも上昇する。板厚が厚くなれば、加工面が多く取れる切削工具の選定や加工パスも考慮する必要がある。 自動車部品の多くは、1回の単発プレスでは加工できないため、順送、トランスファーなど、複数回のプレス加工によって成形される。1回の工程でどこまで曲げるのか、絞るのかなど、熟練のノウハウや金型の精度が必要になる。 余談だが、超ハイテン材のような引っ張り強さが高い素材を常温のまま加工することは難しく、欧州勢はホットプレス(鋼板を900℃程度にしてプレスを行うこと)によって加工する手法を取る場合も多い。しかし、鋼板を熱する工程で多くのCO2が排出されてしまう。超ハイテン材を金型によって冷間加工できるのは日本の金型技術と材料技術が高いことを意味する。■1.5GPaの超ハイテン材の加工を行える協和工業の技術力ここまで見てきたように、日本の自動車産業やモノづくり産業を支える金型だが、最新の取り組みを紹介したい。今回事例として取り上げるのは、静岡県湖西市にある協和工業である。協和工業はプレス金型の製造とプレス加工の両方を担い、自動車サプライヤーに供給している。1.5GPaの超ハイテン材の加工を行える技術を持つことが強みだ。 協和工業は、特定の系列に所属せず独自性を貫く。隣にはスズキの湖西工場が広がるが、過去は日産系がメインの顧客であり、最近のメインの顧客はトヨタ紡織グループが多いとのことだ。先述したようにトヨタ自動車もハイテン材や超ハイテン材の活用を進めている。トヨタ紡織グループは多くの部品をトヨタ自動車にも供給しており、必然的にトヨタ紡織グループに部品を供給している協和工業にも技術の高いプレス金型やプレス加工が要求される。一般的な金型製作工程と課題協和工業の金型製作工程は、多くの金型メーカーが金型を製造する方法と大きく異なっている。多くの金型メーカーは通常、以下のような段取りで進めている。依頼先から送付された仕様(2次元図面や3D CADデータ)を基にして、CAEなどで検証し加工後の形状を加味し、金型の3D CADモデルを起こす3D CADモデルが完成したら、上長や依頼先を交えてDRを行い、モデルの磨き込みをして問題が無ければ出図する当該3D CADモデルや、3D CADモデルから作成された2次元図面を基に、金型部品の加工指示や購買の手配を行う製造現場は、3D CADデータや2次元図面を確認しながらCAMを構築して金型部品を切削によって製造していく切削され精度が担保できた部品と、調達で購入した部品を組み合わせて複雑な金型を組み立てる組み立てられた金型をプレス機に搭載し、鋼板の加工を行う。抜き取り検査などを行った後、部品を出荷する多くの金型メーカーでは、これらのプロセスで金型を製造していくが、寸法公差や幾何(きか)公差は2次元図面上で指定されているため、都度2次元図面を見ながら金型部品の精度を作り込んでいく必要がある。 各寸法や部品の指示は金型設計者にゆだねられているため、設計担当者ごとに微妙に指定する精度が異なったり、部品の仕様が異なったりする。製造(切削)担当者は、図面情報を逸脱した製造はできないため、切削を行う際に図面を何度も確認しなければならない。構成部品は自社だけで製造(調達)できるわけではないため、調達部門からサプライヤーに加工の依頼を行う。もちろんサプライヤーも指示された図面を確認しながら部品を作成する。 本連載を読んでいただいている読者であれば、既に想像できることだろう。このような作業には膨大な付帯作業が発生する。発生する工数は以下のようなものだ。3D CADモデルから2次元図面に転写する工数が発生する3D CADモデルから2次元図面に転写した際、寸法指定や公差の指示漏れが発生しがちだ。その場合、組み立て時に気が付くため手戻りや追加工の手間が発生する調達でも同様の負荷が生まれる。2次元図面で寸法指定や、公差の指示が漏れている場合は、部品受け入れの検収の際では気が付かず、組み付け作業や金型納品時に気が付くことになり、部品を特急で手配することになる。特急部品は高くなり原価を圧迫する担当者ごとに独自ルールがある場合は、加工作業が標準化されておらず、不必要な加工がなされることもある(QCを満たすために不要な加工である場合もあるだろう)3次元測定器を用いた精度の確認も、3D CADモデルにPMIを持たせれば、測定パスを滞りなく構築できるが、2次元では図面を見ながら測定パスを都度構築する必要がある 従来の金型に関するモノづくりプロセスは、統一されたデータがないことでこれらの課題が常に発生している状態にあった。■PLMを活用した協和工業の金型製造工程このように、一般的な金型製造では、データと図面の行き来をしているために、多くのムダやムラが存在している。しかし協和工業はそうではない。協和工業は昔から、一括でBOM情報を管理する仕組みを構築し、ムダやムラのない金型製作に取り組んでいるためだ。 協和工業では、Cimatron(CAD/CAMソフト)を軸にPLMの運用を進めており、E-BOM(金型を設計する際の部品情報)を構成する際にあらゆる加工、部品データを定義している。顧客先から提供された製品CADモデルから金型のCADモデルを構築する際に、寸法や公差情報を確定すると同時に、精度による色分けと全ての加工工程を決定する。つまり、設計する際に製造プロセスも自ずと決定する形となっているのだ(BOPの自動生成)。さらに精度以外にも、設計時に以下のような情報を定義していく。各部品の型番寸法公差、幾何公差内製品か購入品材質熱処理やコーティング加工※金型の3Dモデル 出所:協和工業 既に設計段階で加工工程が定義されていることから、あとはCADを取り込んだCAMソフト上で範囲選択によって対象加工物を一括で選択するだけで、加工パスが生成される(割り当てされる)のだ。穴についても同様で、範囲選択をするだけで全ての穴の加工パスが確定される。 このすごさが伝わりづらいかもしれないので少し細かく説明すると、通常は加工の部位ごとに加工パスを設定していく必要がある。どのようなツールホルダを使用するのか、どのような切削工具を使用するのか、どのような切削速度にするのか、切削方法はどうするのかなどをそれぞれ設定していかなければならない。しかし、協和工業のようなやり方を取れば、面加工も穴加工もタップ加工も面取り加工なども、対象ワークをマウスで範囲選択することによって一瞬で終えられる。範囲選択をすると一瞬で全ての穴加工の加工パスが生成される 出所:協和工業 このようなことができるのは、CADモデルを設計、構築する際に、精緻にBOM情報(各部品の寸法情報や加工情報)を決めているためだ。 CADモデルが確定されるDR段階においても、設計、製造現場、調達が一緒になって確認をするため、非常に多くの工数が必要になっているように見えるが、設計以降の作業が激減されるため、全体の工程を考えれば生産性は高まっている。さらに穴加工や部材情報なども標準化されており、使用するボルトやガイドポストなども自動で決まるため、設計段階で発注のリストも出来上がるといってよい。■CimatronだからできるBOM管理多くのCAMソフトはBOMに対してここまで多くの情報を保持させることができず、CAMは単なる加工パスを生成するソフトウェアという位置付けだが、先述した通りCimatronにはさまざまなBOM情報を持たせることが可能だ。また、持たせる情報は任意に決めることができるなど、自由度が高い。 最初の設計段階でBOMにさまざまな情報を持たせることによって、加工情報の付与漏れを防ぐことができるので加工漏れによる手戻りや、発注ミスなども激減した。また、加工のために2次元図面を起こすことが不要となり、本来であれば行う必要がない付帯作業も削減できるようになった。 組み立て作業も、金型を組み立てる現場が3Dモデルを見ることによって、誰でも簡単に理解できるようになった。設計から製造、組み立てまで同じデータを利用することで、滞りや重複がないようにしている。これにより、生産性は2倍以上になったという。デジタル技術を生かした素晴らしい運用変革である。組み立て現場でも3D CADモデルを確認しながら作業を行う 出所:筆者撮影■協和工業のBOM運用はまだまだ広がる協和工業のBOM管理は金型の設計から組み立てのみにとどまらない。部品1個1個、プレート1個1個のBOM情報を管理することが可能になり、ERPと連携させることによって、金型の製造に必要なコストがリアルタイムで分かるようになった。 現場の加工指示書にはバーコードが印字されており、業務の始まりと終わりに読み込むことで部品加工時間が分かるようになっている。実際のコストと想定コストを突き合わせることで精緻な金型コストが分かるようになる。指示書 出所:筆者撮影 切削に必要になる時間や、購入品のコストを設計者が理解しながら金型を設計できるようになる。全てデータの裏付けがある形となり、カンとコツ、どんぶり勘定に頼る現場と圧倒的な隔たりが生まれることになる。金型は足の長い商品となるため、できる限り適正な製造コストを導き出さなければならない。 この「足が長い」という点を、もう少し細かく記載すると、金型は、製造した後、金型もしくは金型によって生み出される製品を納入するまで、現金を回収できないのだ。長いもので金型の製造には6カ月程度必要になることもあるので、キャッシュフローの維持が会社運営には非常に重要になってくる。さらに、(最近は少なくなっていると聞くが)昔は手形の受け渡しの場合もあった。手形は現金化するまで時間が必要になるため、銀行に手数料を払い現金化する企業も存在するほどだ。厳しい経営環境の中で、金型のコストが精緻に分からず上振れすることはキャッシュフローを圧迫し、従業員への給与の支払いが滞り最悪の場合は死に直結する。 協和工業のBOM運用は、精緻なコストが分かるだけではなく、プレス工程までつながる。プレスを打つ量産現場との連携も行い、最適な金型を定義していくのだ。では、「最適な金型」とは何なのだろうか。 金型はプレス機に搭載されて、鋼板の形を変形して初めて工業的価値を発揮する。協和工業の金型は自動車部品を製造するために使用されるため、何万回もプレスを行う。世界的ヒット商品の生産では、(順送の場合)数百万回も金型を打つことになるので、当然金型は劣化する。超ハイテン材の様な強度のある金属材を金属で切断するので、金型の刃先は金属がこすれ合い、温度も上昇するため劣化、摩耗していく。 金型の一部が生産によって摩耗する場合は、摩耗した部分のみを取り換えるのか、金型の部材全体を研削で削り取り、高さ調整のため削り取った厚み分だけシムプレートを入れ込むのか判断しなければならない。同じ金型の写真である。右図の赤枠内の部品はボルトで付け替えが可能だ 出所:協和工業 摩耗した部分のみ変更する場合は、部品が複数個になるため製造コストは上昇するが、メンテナンスは(一部の部品取替えで済むため)コストがかからない。しかし、一体物として構成する場合、製造コストは一括で切削できるため高くないが、メンテナンスは全体の切削やシムプレートの取り付けなどが必要になるため時間もコストも必要になる。 協和工業はBOMに製造時や保守メンテナンス時のコストも反映可能だ。生産が突発で止まり、メンテナンスが起こった際に要因を記録しアラートが立つ仕組みを構築している。金型の製造コストだけではなく設計が製造に与えた問題の要因までを分析できるようにしている。 例えば、品質不適合が起こり金型を修正する必要が出たとする。そうなると金型の取り外し、取り付け、金型の修正などで8時間生産が停止する。この8時間分の人件費や修正コストをBOMにひも付けて、金型の製造コストだけではなく、製造や修繕に必要になった工数を含めた「全体のコスト」を把握できる。これにより「最適な金型」を追求しているのだ。 もちろん、生産動態から金型設計に問題があった場合は、CAEのモデルを最適化して対応している。超ハイテン材のような材料はまだ活用されだして日が浅く、CAEのシミュレーションも完璧ではなく、現場の生産から得られる実データをフィードバックすることでCAEの精度も上げている。 あらゆる工程でBOMを中心とした運用を実現し、それをERPと連携させることで、どのような金型設計をすれば最適な金型の運用ができるのか、一番もうけが出せるのかをデータから冷静に判断できるようになる。製造でどのような作業が必要になったのかを示すリスト 出所:筆者撮影■金型にもPLMの運用を このような金型製作において高度なPLM運用は、大手製造業でしか運用することができなかった。筆者が日産自動車のタイの金型工場を訪問した際は、設計時にBOPを構成するなど高度なPLM運用を目にすることができたが、今では市販のデジタルツールを利用することで中規模の製造業の事業者でも活用できるようになっている。 現に協和工業では、Cimatronを使いBOMを中心とした情報の整理を行い、ソフトに最適な業務フローを構築することで設計BOMから製造BOMに反映する高度な運用と、製造情報から設計の最適化ができるようになっている。 10年以上同じような業務フローを続けている企業は、一度自社の運用が最適な運用なのか自問自答していただきたい。もちろん助力が必要であれば、金型メーカー問わず、車載メーカーや半導体製造装置、重工業などあらゆる支援を行っている筆者に一度お声がけをいただきたい。貴社の業務フローの見直しもお手伝いさせていただければ幸いである。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー記事はコチラ↓https://monoist.itmedia.co.jp/mn/articles/2509/09/news123.html


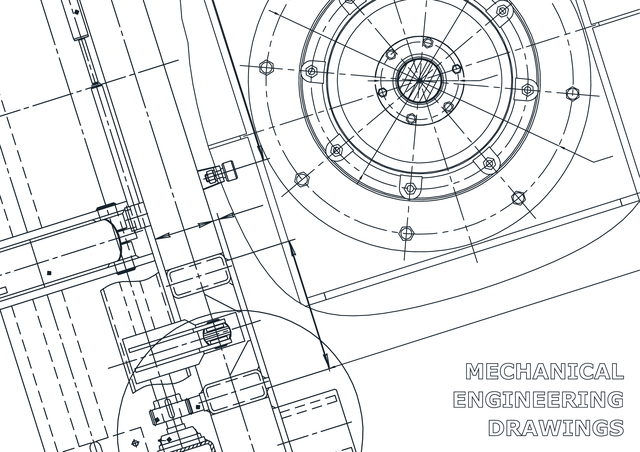



.png&w=828&q=75)
.png&w=828&q=75)


